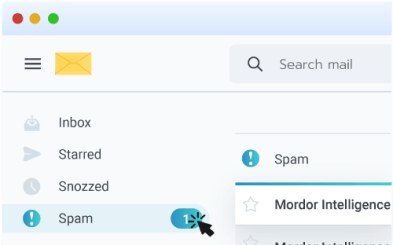日本のコールドチェーン物流市場分析
日本のコールドチェーンロジスティクス市場規模は2025年に214.9億米ドルと推定され、予測期間中(2025-2030年)の年平均成長率は5%で、2030年には274.2億米ドルに達すると予測される。
東京圏と大阪圏では、旺盛な需要にもかかわらず、物流セクターは供給過剰の問題に取り組んでいる。新規物流施設の供給過剰は、空室率の上昇と賃料の下落を招き、デベロッパーは競争力を維持するための技術革新を余儀なくされている。
日本市場は、消費者の間で高まっている新鮮で高品質な製品に対する需要に後押しされ、成長軌道に乗っている。特に予防接種と継続的な健康管理への関心の高まりが、この成長を後押ししている。
この分野では、温度の影響を受けやすい医薬品やワクチンを流通させるために、高度なロジスティクスへの依存度が高まっている。さらに、冷蔵およびロジスティクス技術の進歩は、業務をより効率的でコスト効率の高いものにしており、この分野の可能性をさらに高めている。
この成長をさらに後押ししているのは、日本の厳しい規制により、生鮮品や医薬品の輸送に高度なコールドチェーン・ソリューションが義務付けられており、コンプライアンスと安全性の両方が確保されていることである。オンライン食料品ショッピングの急増により、市場も拡大している。
Eコマース・プラットフォームや小売業者は、生鮮品を迅速かつ安全に配送したいという需要の高まりに対応するため、コールドチェーン機能に多額の投資を行っている。こうした要因が総合的に、日本のコールドチェーン・ロジスティクスの急速な進化と拡大を裏付けている。
冷蔵倉庫は摂氏10度以下の温度を維持する。消費者や規制当局の衛生に対する関心の高まりが、汚染や腐敗を防ぐための信頼性の高いコールドチェーン・ソリューションの必要性を高めている。
医薬品セクターの成長により、有効性と規制基準の両方に沿った、保管と流通のための厳格な温度管理が義務付けられている。輸入の増加に伴い、日本では生鮮食品や医薬品を含む生鮮品の増加が見られる。
都市化はスーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンライン食料品プラットフォームの成長に拍車をかけており、これらすべてが、消費者に新鮮な製品をタイムリーに届けるための効率的なコールドチェーン・オペレーションを要求している。
結論として、日本のコールドチェーン・ロジスティクス分野は、新鮮で品質に敏感な製品に対する消費者需要の増加、 堅固な医薬品部門、および厳しい政府規制によって、大きく成長する態勢にある。
技術の進歩と電子商取引の台頭は、この分野の将来性をさらに高めている。開発業者や小売業者がコールドチェーン機能の革新と投資を続ける中、市場は拡大し、生鮮品の効率的で安全な全国配送が確保されると予想される。
日本のコールドチェーン物流市場動向
物流・倉庫部門が大幅な伸びを見せる
旺盛な需要の中、東京圏と大阪圏の物流セクターは新規供給の急増に直面しており、需要と供給の微妙なバランスが崩れている。このような流入は空室率の上昇と賃料の下落を招き、デベロッパーは競争力を維持するためのイノベーションを余儀なくされている。
テナント確保に苦戦しているところもあるが、一等地の立地と冷蔵倉庫機能を誇る物件は依然として高い人気を誇っている。予測によれば、2023年の新規供給量は2022年の数字を上回り、特に東京圏では過去最高を記録する見込みである。この供給急増はテナント獲得競争を激化させ、特に立地の悪い施設や古い施設は不利になると予想される。
2023年上半期、大東京の竣工面積は顕著に増加し、300万㎡近い新規物流スペースが導入された。目立ったのはESR東扇島ディストリビューションセンターで、34万9,000平方メートルのマルチテナント型施設であり、現在では日本で最も高い物流ビルとして認知されている。逆に、同時期のグレーター大阪の新規供給はより抑制的で、総面積は約52万平方メートル、2023年に10万平方メートルを超える開発はなかった。
注目はMCUD神戸西IIで、GFA6.3万㎡を誇り、神戸テクノ・ロジスティクスパーク内に戦略的に立地し、主要道路や高速道路に近接しているため、効率的な配送と旺盛な労働力を提供する。2023年に竣工した大和ハウスDPL兵庫川西は総面積89,000㎡で、川西インターチェンジに近接し、西日本エリアへのアクセスを強化する戦略的な立地となっている。
2023年には合計で約100万㎡の新規供給があり、2024年からはグレーター大阪での開発活動が大幅に増加すると予測されている。2024年7月には、日本での存在感で知られる大和ハウス・ロジスティクス・トラストが、ホーチミン市近郊の新築倉庫を4,830億VND(2,000万米ドル)で取得し、事業範囲を拡大した。1区から車で1時間の距離にあるこの倉庫は、同年9月に完成した最新鋭の冷蔵倉庫を備えている。
2022年、神奈川県の冷蔵倉庫容量は約445万立方メートルで日本最大だった。東京都は約386万立方メートルでこれに続く。冷蔵倉庫とは、商品を10℃以下で保管する施設と定義される。
結論として、東京圏と大阪圏の物流セクターは、新規供給の流入により大きな変化を遂げつつある。これは、空室の増加や賃料の低下といった課題を生み出す一方で、デベロッパーのイノベーションを促す要因にもなっている。一等地の立地と先進的な機能を備えた施設は引き続き活況を呈しており、戦略的なポジショニングと最新設備の重要性が浮き彫りになっている。市場の進化に伴い、関係者は競争力を維持し、新たな機会を活用するために、力学の変化に適応しなければならない。

日本の製薬セクターの成長
高齢化社会を追い風に、日本は世界の医薬品業界において傑出した存在となっている。この国は、米国に次ぐ強固な国内生物製剤部門を誇るだけでなく、最先端の医療技術の生産と輸入を積極的に支持している。これを後押しするように、日本政府はジェネリック医薬品を熱心に提唱してきた。
日本は歴史的に、革新的な医薬品メーカーに独占権を与えることを好んできた。ジェネリック医薬品を受け入れるという点で、日本は他の先進国市場とより密接な関係を築きつつある。これは、費用対効果の高い代替品を求める政府の動きと相まって、バイオシミラー医薬品のビジネスチャンスを大きく拡大する舞台となっている。
日本国内の製薬企業はますます海外に目を向けるようになっており、海外売上高は顕著に増加している。このような世界的な拡大は、コールドチェーン保管・輸送施設に対する需要の高まりに拍車をかけている。さらに、日本の製薬業界では、日本の創薬エコシステムを強化する可能性が注目されている。
日本の製薬大手とAIスタートアップのコラボレーションは増加傾向にある。製薬業界の新薬開発の状況は厳しく、成功率は2万から3万分の1と推定され、開発期間は10年以上かかる。このような試みは、平均約1200億円(約834百万米ドル)という高額な価格タグを伴う。
2022年、日本の医薬品輸入額は3兆4,000億円を超え、前年より増加した。同時に、2022年の日本の医薬品輸出額は約6,490億円に達し、前年の約5,630億円から増加する。
コールドチェーン・ロジスティクスは医薬品セクターにおいて極めて重要な役割を果たしており、医薬品やワクチンが厳格な温度要件を遵守することを保証している。これは特にワクチンにとって極めて重要であり、特に大規模な予防接種プログラムにおいては、その効力と効能を守ることになる。
結論として、日本の医薬品市場は、政府の取り組み、技術の進歩、世界的な拡大努力に牽引され、大きく成長する態勢にある。AI新興企業との協業の増加やコールドチェーン物流に対する需要の高まりは、この分野のダイナミックな進化をさらに際立たせている。日本が創薬エコシステムの強化を続ける中、世界の製薬業界における重要なプレーヤーであり続ける。

日本コールドチェーン物流業界の概要
市場は比較的断片化されており、日本通運、ヤマト、佐川急便、伊藤忠ロジスティクス、近鉄エクスプレスなど、国内外に多数のプレーヤーがいる。市場の競争は、コスト、保管料、スペース、梱包・包装資材の価格上昇に関連している。サービス・プロバイダーは、プロセスの標準化を提供する能力の開発にまだ取り組んでいる。保管温度や作業手順に関する標準化の欠如は、業界が直面するさらにいくつかの重大な課題である。利用可能な冷蔵倉庫スペースの質と柔軟性は、かなりの懸念事項である。
日本のコールドチェーン物流市場のリーダー
Nippon Express
Yamato Transport Co.
Sagawa Express Co.,Ltd
Kintetsu World Express
Itochu Logistics Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同

日本コールドチェーン物流市場ニュース
- 2024年6月佛山ハイブ・キャピタル・マネジメントは、姉妹会社であるイデラ・キャピタル・マネジメントと共同で、グレーター大阪における冷蔵倉庫物流プロジェクトの前倒し購入に焦点を当てた合弁事業を開始した。プロジェクトの初期段階では、150億円(1億米ドル相当)の出資を受け、特殊な冷蔵倉庫資産のポートフォリオを構築する。パートナーは、大阪のベンチャー企業について、1万平方メートル(107,639平方フィート)を超える賃貸可能面積を誇る、エネルギー効率の高い施設であると説明している。完成予定は2025年後半で、この開発はJVの最初の買収となり、Fosun Hiveがファンドマネジメントを、Ideraがアセットマネジメントを担当する。
- 2023年4月GLPは日本で55,000平方メートル(SQM)の完全冷蔵クール貯蔵施設の建設を開始しました。GLP Pte Ltd(GLP)は、GLPコシオ島およびGLP六甲Vの日本における専用物流開発施設として、グローバルなコールドチェーン業界の高まる需要に対応します。
日本のコールドチェーン物流産業のセグメント化
コールドチェーンとは、特に食品、医薬品、その他温度に敏感な製品の温度管理された生産、輸送、保管、流通を促進するシームレスな物流・業務プロセスである。国際連合食糧農業機関(FAO)によると、コールドチェーンは予冷、貯蔵、輸送、流通、小売、そして家庭内の冷蔵段階までを含む。
日本コールドチェーンロジスティクス市場の完全な背景分析として、経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントの新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響などを含みます。
日本のコールドチェーン物流市場は、サービス別(保管、輸送、付加価値サービス(ブラスト冷凍、ラベリング、在庫管理など))、温度タイプ別(チルド、冷凍)、用途別(園芸(生鮮果物・野菜)、乳製品(牛乳、アイスクリーム、バターなど)、食肉、魚、鶏肉、加工食品、医薬品、ライフサイエンス、化学品、その他の用途)に分類されています。本レポートでは、日本のコールドチェーンロジスティクス市場について、上記の全セグメントの市場規模および予測を金額(米ドル)で提供しています。
| ストレージ |
| 交通機関 |
| 付加価値サービス(急速冷凍、ラベリング、在庫管理など) |
| 冷蔵 |
| 凍った |
| 園芸(新鮮な果物と野菜) |
| 乳製品(牛乳、アイスクリーム、バターなど) |
| 肉類、魚類、鶏肉 |
| 加工食品 |
| 製薬、ライフサイエンス、化学 |
| その他のアプリケーション |
| サービス別 | ストレージ |
| 交通機関 | |
| 付加価値サービス(急速冷凍、ラベリング、在庫管理など) | |
| 温度タイプ別 | 冷蔵 |
| 凍った | |
| アプリケーション別 | 園芸(新鮮な果物と野菜) |
| 乳製品(牛乳、アイスクリーム、バターなど) | |
| 肉類、魚類、鶏肉 | |
| 加工食品 | |
| 製薬、ライフサイエンス、化学 | |
| その他のアプリケーション |
よく寄せられる質問
日本のコールドチェーン物流市場の規模は?
日本のコールドチェーンロジスティクス市場規模は、2025年には214.9億米ドルに達し、年平均成長率5%で成長し、2030年には274.2億米ドルに達すると予測される。
現在の日本のコールドチェーン物流市場規模は?
2025年、日本のコールドチェーンロジスティクス市場規模は214.9億米ドルに達すると予測される。
日本のコールドチェーン物流市場の主要プレーヤーは?
日本通運、ヤマト運輸、佐川急便、近鉄エクスプレス、伊藤忠ロジスティクスが日本のコールドチェーン物流市場で事業を展開している主要企業である。
この日本のコールドチェーン物流市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は?
2024年の日本コールドチェーン物流市場規模は204.2億米ドルと推定されます。本レポートでは、日本のコールドチェーン物流市場の2021年、2022年、2023年、2024年の過去の市場規模を調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の日本コールドチェーン物流市場規模を予測しています。
最終更新日:
日本のコールドチェーン物流市場をサービス、温度タイプ、用途別に分類。市場規模および予測はすべてのセグメントについて金額で提供されます。当業界レポートでは、日本のコールドチェーンロジスティクス分野における市場シェア、業界分析、市場成長を明らかにしています。市場予測展望と過去の概要も記載しています。
業界研究では、園芸、乳製品、食肉、魚、鶏肉、加工食品、製薬、ライフサイエンス、化学など様々な用途をカバーしています。市場分析では、最大手企業とその市場動向への貢献に焦点を当てています。業界の見通しは、市場価値を牽引する重要なマーケットリーダーにより、プラスの成長率を示しています。
当市場レポートは、詳細な市場データと産業統計を提供する包括的な産業調査資料です。市場レビューと市場セグメンテーションにより、市場の構造とダイナミクスに関する洞察が得られます。レポート例とレポートPDFは、さらなる参考のためにご利用いただけます。
この分析書に掲載されている業界レポートおよび業界情報により、市場の現状と将来予測を完全に理解することができます。市場概要と市場予測は、利害関係者が情報に基づいた意思決定を行うために不可欠です。業界売上高と業界規模は、市場パフォーマンスを評価するための重要な指標です。
まとめると、日本のコールドチェーンロジスティクス市場は、業界動向と市場リーダーに支えられ、大きな成長を遂げようとしています。市場予測と市場展望は、様々な用途における継続的な拡大と機会を示唆しています。本レポートは、市場の展望と可能性を理解するための貴重な資料となります。